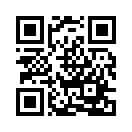2009年01月13日
京都の地図には見慣れない地名がたくさん載っています
地名の由来を調べてみませんか?きっと文化や歴史に関する面白い発見があるはずです。私はそのことを、頻繁に京都散策するようになり実感しました。
糺の森、深泥池、 椥辻、紫竹・・・京都を散策していると、読み方すら分からない地名を、あちこちで見かけます。
京都の地図には見慣れない地名がたくさん載っています。不思議に思った私は、図書館へと向かいました。そこで、京都の地名に関する興味深い事実を、たくさん知ることになるのです。
京都は、千二百年の都として、また宗教の中心地として知られています。神道や仏教に関係する地名が数多く存在するのもそのせいでしょう。
例を挙げてみましょう。川床で知られる貴船という地名は、日本神話に出てくる玉依姫という神が、黄色い船で川でたどり着き、祠を建てた場所と言われています。
僧侶が百万回念仏を唱えたから百万遍・・という地名もあります。左京区にあるこの地名は、元弘元年、蔓延する疫病を鎮めようと、知恩寺の空円が百万遍念仏を行ったことが起源となっています。面白いですね!
ちょっとホラーな地名もあります。京都では、化野、紫野、鳥辺野、蓮台野など、「野」のつく地名は全て、かつての風葬地だったそうです。
これには、地名における「野」という字に葬送の意味を持たせる京都独特の表現が影響しているようです。
その中でも不気味さで群を抜くのが鳥辺野という地名の由来です。この地名は、木に吊るした人間の遺体を鳥に食べさせる「鳥葬」が行われていたことから付けられたそうです。
ガイドブックが載せていない、その土地の文化や歴史に導いてくれる・・それが地名なのかもしれません。たかが地名、されど地名です。
地名にも、人と同じように様々な歴史や背景があるのでしょう。他にももっと驚くような地名があるはず。調査してみたいです!
自分の出身地や旅行先・・これからは京都以外でも、地名の由来を調査してしたいなと思っています。