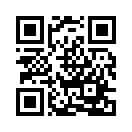2009年08月16日
糺の森、深泥池、 椥辻、紫竹・・京都を歩いていると
「地名が付けられた背景には、その土地の文化や歴史が潜んでいる。」私がそのことに気づいたのは、度々京都へ遊びに行くようになってからのことです。
京都には、糺の森、深泥池、 椥辻、紫竹など、読み方すら分からないような地名や通り名が溢れています。
京都を散策中に地図を眺めていると、必ずといっても不思議な地名にぶつかります。そこで私は図書館へ向かい、地名の由来を調査!たくさんの興味深い由来を発見することができました。
千二百年もの間、日本の都であり続けた京都。神道や仏教といった宗教も栄え、それらに関する地名が、現在も多く見受けられます。
例えば、日本神話に登場する神様が由来になっている地名もあります。川床で有名な貴船は、玉依姫が黄色い船でやって来て、祠を設けた場所と伝えられています。
「へ~」と呟いてしまった由来は、左京区の百万遍。この地名が名付けられたきっかけは、鎌倉末期に京都で流行病が広まったことでした。病気を鎮めるため、空円という知恩寺の僧が百万回念仏を唱えたことに由来しているのです。
ちょっとホラーな地名もあります。京都では、化野、紫野、鳥辺野、蓮台野など、「野」のつく地名は全て、かつての風葬地だったそうです。
これは京都の地名に限られたことのようですが、「野」という字に葬送の意味を持たせているのです。
「鳥葬」が行われていたから鳥辺野、という地名もあります。東山五条近くにあるこの土地では、かつて人の死体を木に吊るし、それを鳥に喰らわせていたのです。き、気味が悪い・・。
地名の由来を調べることで、他では得られないその土地の情報を得られるかもしれません。たかが地名と侮るなかれ!です。
「人に歴史あり」といいますが、地名にも歴史があるのですね。もっともっと、面白そうな地名や通りの由来を知りたくなってきました。
自分の出身地や旅行先・・これからは京都以外でも、地名の由来を調査してしたいなと思っています。