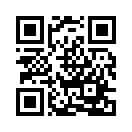2011年10月24日
公園で子供たちが仲良く皆で遊んでいるな、と思いきや!
外に元気に飛び出した子どもたちも、公園で追いかけっこをするでなく、固まってゲームに集中、という光景も多くなりましたよね。
幼い頃、ゲームしよう、と言って思い浮かぶのは、部屋の中でやるトランプなどのカードゲームや、盤と駒を使ったチェスやオセロなどのボードゲームのような、テーブルゲームを指していたように思います。
しかし、現在ゲームと言ったら携帯できるDSやPSPであったり、テレビゲームのWii、PSに代表される、コンピュータゲームを指すでしょう。
そのコンピュータゲーム、登場当時ブームになったのはレトロ感いっぱいのインベーダーゲームや、ブロック崩しなど。テーブルがゲーム機の「ゲーム喫茶」という言葉も懐かしいですね。
コンピュータゲームは、登場当時のシューティングゲームだけでなく、その後はロールプレイング、アクション、レースへとゲーム内容は増えていき、昨今では、ドリル系の語学、雑学、歴史などの知的部分に訴えたり、美容や料理など好奇心を満たせる内容のゲームも増えてきました。
人々の間で知られているこれらのゲームと言えば、DSソフト「脳トレ」「英語漬け」などの、「かつて子どもだったオトナたち」へ向けた、子ども向けではないゲームソフトでしょう。
しかし、これらのコンピュータゲームで知識は得られても、カードゲームやボードゲームなどの、生身の人間相手で、表情を見ながら駆け引きをして勝敗へ繋げるというやりとりの体験は出来ません。
そこで登場したのコンピュータゲームは「育成シュミレーション」。これならば、自分の感情をコンピュータゲーム上に投影できるとして、「たまごっち」「シーマン」などで人気が出ました。また、育成できるのは生き物だけでなく、サッカーチームや野球チームなど、組織や団体も育成できるようなものが増えました。
また、これらが発展して「ギャルゲー」「アダルトゲーム」と言われるような、ゲームの登場者に恋愛感情を抱かせたり、感動させるような内容のゲームも出てきました。
しかし、この恋愛が体験できるようなゲームの登場で、面倒な生身の人間相手ではなく、コンピュータゲームの中で自分の感情を満たすプレイヤーも多くなったのではないでしょうか。
このようなゲームは、登場者との関係を変えられ、プレイヤーにとって都合よく操作できますが、生身の人間関係ではそんな簡単に流れを変えることはできませんよね。
黙々と公園で携帯ゲームにいそしむ子供たちの集団。この子供たちが大きくなっても、ゲーム内で全ての好奇心や感情を使い切ることなく、生身の人間のふれあいが大切であることを感じていて欲しいものですよね。